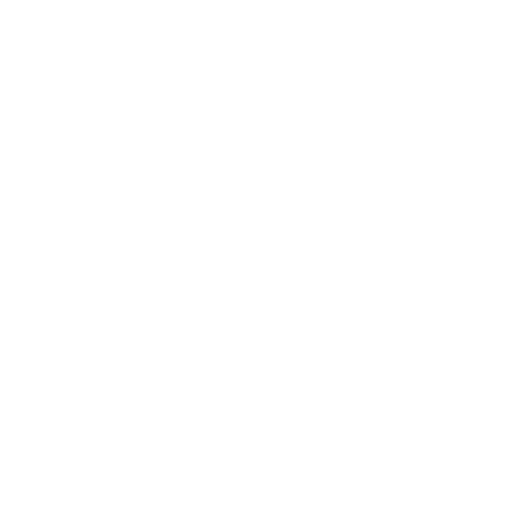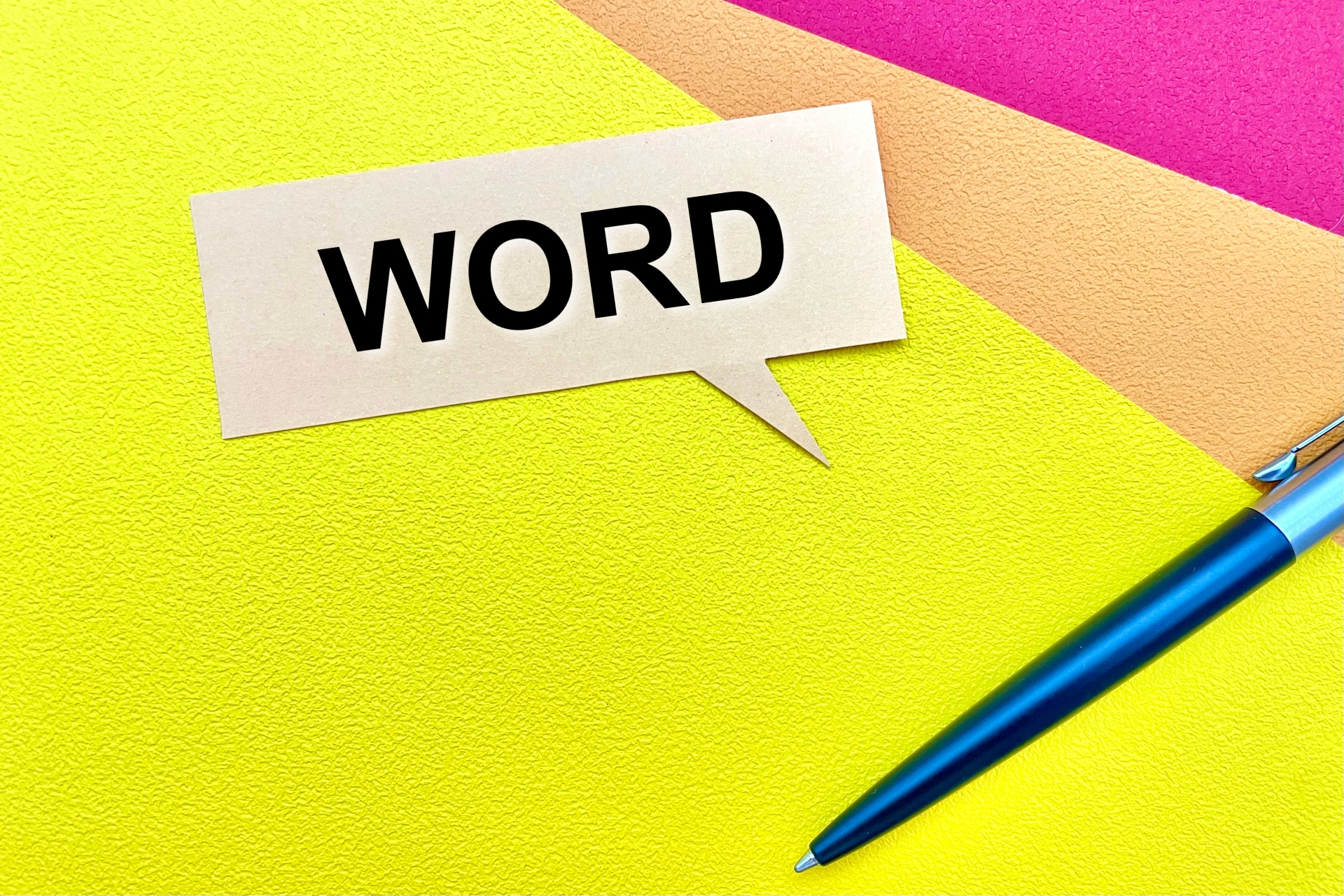介護
投稿日:2023/07/04
更新日:2024/10/14
介護認定調査とは?流れと手続きから結果受け取りまでの流れを解説
.png)
目次

介護認定調査の概要と目的
要介護認定調査は、介護保険を利用する際に必要な調査となっています。
公的な介護保険サービスを受けるための基準となりますが、実際にどのような仕組みとなっているか、
また認定対象者の範囲や申請から認定までの手続きについても詳しく見ていきましょう。
要介護認定とは
要介護認定は介護保険制度において、寝たきりや痴呆などで介護が必要な状態や、日常生活の支援が必要な状態を7段階の数値で判定する制度です。
要介護認定を受けることで公的な介護保険サービスを受けることができます。
自宅で生活を続ける際には、生活援助や身体介護が受けられる他、必要に応じて施設入居も可能です。
要介護認定は8区分に分類され、数字が大きいほど介護の必要性が高く、審査により判定されます。
認定を受けることで介護保険サービスを1〜3割の自己負担で利用できます。
認定対象者の範囲
認定基準はどうなっている?
要介護度は要介護認定等基準時間に基づいて判定されます。
この基準時間は介護に費やす手間や労力を時間に換算した指標であり、症状が重いほど時間が長くなります。
要介護認定は日常生活の8つの場面ごとの行為時間と「認知症」の時間を加算して算出されます。
持病や年齢だけでなく、症状によって要介護度は異なることがあります。認定によって受けられるサービスや給付金の額も異なり、
全国一律で定量的な基準が必要です。要介護認定は介護の手間を評価し、時間に換算して判定されます。
要介護と要支援の違い
「要支援」と「要介護」は、日常で必要な介護(介助)の度合いを示すものです。
要介護の方がより重度で、日常生活全般での介護が必要な状態と言えます。
認定によって利用できるサービス内容や負担額が変わります。
要支援は基本的に一人で生活できるが一部介助が必要な状態であり、介護予防サービスを利用できます。
要介護は日常生活全般で誰かの介護が必要であり、介護サービスを受けられます。
認知機能の低下がある場合は要介護に分類されることが多いが、軽い症状なら要支援になる場合もあります。
要介護の方が要支援よりも手厚い支援を必要としていることがわかります。

介護認定調査の流れと手続き

申請から訪問調査まで
要介護認定の申請には本人または家族が市区町村に申請書と必要書類を提出します。
申請書と介護保険被保険者証が必要で、40~64歳の場合は健康保険の保険証も必要です。
主治医意見書も提出が必要で、主治医がいない場合は指定医の診察が必要です。
要介護認定調査を受ける場合、事前準備が重要であり、調査内容や普段の介護内容を確認してメモを取ると適切な判断が得られる可能性が高まります。
既往歴や困り事、要望もまとめて伝えやすくしておくと良いです。
調査員による判断
要介護認定の調査は、市区町村の職員が訪問して、心身の状況に関する調査を行います。
調査は74項目の基本調査と特記事項からなります。
基本調査は6つの項目に基づいて詳しく心身の状態を確認し、概況調査では利用中のサービスや家族状況、自宅の状況などを確認します。
介護認定調査には「身体機能・起居動作」「生活機能」「認知機能」「精神・行動障害」「社会生活への適応」の5つの基本調査項目があり、
調査の結果はコンピューターによる一次判定を経て決定されます。
審査判定
要介護認定の二次判定は、一次判定の結果やかかりつけ医の意見書、調査の特記事項を基に、保健・医療・福祉の専門家が行います。
この判定は介護認定審査会によって行われます。
審査会では、一次判定結果と訪問調査の特記事項、そして主治医の意見書を元にして、要介護の程度や必要なサービスの内容が審査され、最終的な認定が行われます。
二次判定によって、要支援または要介護の区分が決定され、その後の介護サービスや給付金の内容が決まります。
認 定
介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が通知されます。
通常、申請から結果通知までは約30日程度かかりますが、地域によっては1〜2か月かかる場合もあります。
要支援1〜2の場合は介護予防サービスが利用でき、要介護1〜5の場合は介護保険サービスが利用できます。
認定結果に納得がいかない場合は、自治体の窓口へ相談し、不服の申し立てをすることも可能です。
この記事の著者
おすすめ記事
関連記事



介護派遣のお仕事に関する
お問い合わせ・ご相談もお気軽に
静岡・関東を中心に介護派遣を専門に行うLASHIC-careerのコーディネーターが丁寧にご相談にのります。介護派遣に関すること、介護の転職に関することなどなんでもお問い合わせください!
お問い合わせフォーム